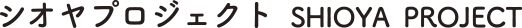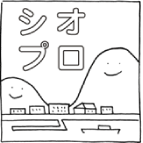独特な感覚にもとづいた作品を発表した明石の誇る文学者、稲垣足穂。小学生の頃、大阪から祖父母のいた明石に移住し、神戸で育つ。その後、数度の上京を経て、30代で再び明石に戻る。家業を継ぐが経営難で困窮、東京、京都と移り住み、それまでの著作の改稿なども多く手がける。選集を読むと、同じ事柄を取り上げた文章が何度も出てくるのはそのため。1960年代後半になって三島由紀夫によって「昭和文学のもつとも微妙な花の一つである」と再評価されたこともあり、晩年は「タルホ」ブームさえ巻き起こる。
そんな稲垣足穂が明石について書いた文章にちらりと塩屋が登場するので、以下に、少し前から引用する。
町の西方を海に注いでいる川に沿って、東北へ十二、三キロ、伊川谷村前開に、藤原鎌足に縁故のある古刹がある。私は、もう三十才をすぎた頃、初めてこの太山寺へ出かけ、背後の丘山に立って、やってきた方を振り返った。
明石川にきざまれた洪積層の台地には、段丘が発達している。ちょっと見ると敷き伸べた緑色のびろうどであるが、それには、黄・樺・灰色・褪紅、いろいろあって、このじゅうたんが段々を作って次第に低まり、ついに横に引いた瑠璃色のリボンである海に接している所…………くろずんだ松木立の中にチョークの二点としてお城の櫓がおかれている辺り…………さすが「前開」の名に背かない展望であったが、同時に、我が住む土地の、まるでガラス粉をぶち撒いたかのような眩しさを、私はいまさらに知った。岡本の里に谷崎潤一郎をたずねて、「そんなら塩屋、それとも舞子辺りに住まわれたらどうか」と口に出して、「いや、あの辺は明るすぎて、とても—」と言下に退けられたことを思い合わした。宇野浩二の短篇にも、阪神間の風光を述べて、「どこを見ても白チョークをでも塗ったような道」とあった。—「どうもあの辺は睡いような景色だね」いつか東京の友人が洩した。
「明石」『タルホ大阪・明石年代記』稲垣足穂 (もとは『明石』(小山書店)収録 昭和23年 1948)
谷崎潤一郎には「明るすぎ」た塩屋。やはり『陰影礼賛』の著者には影が不可欠なのだろう。
「どこを見ても白チョークをでも塗ったような道」は、アスファルト舗装をされた道がほとんどとなった現代では想像するよりほかないけれど、塩屋駅の南(海)側に出て国道2号線沿いを東へ向かって歩くとき、遮るものがなく、直射日光に照らされて眩しいような印象を受けることが多い。瀬戸内の港町の「睡いような景色」も共感するところがある。有名な与謝蕪村の「春の海ひねもすのたりのたりかな」の句も須磨浦で詠まれた可能性が高いと言われているし、確かに、阪神から淡路島までわずかに紀淡海峡のみの開口で対岸がほぼ陸地で繋がった内海である大阪湾の眺めは、よほどの暴風波浪でない限り、睡くなるような穏やかさだ。この明るさ、白さは、平地の占める範囲の広くなる明石の海べりではいや増す。
まかり間違って谷崎潤一郎が塩屋に住んでいたとしたら、どんな『海街diary』だったかと夢想するが、戦前昭和の阪神間お嬢四姉妹物語『細雪』は岡本の倚松庵でこそ生まれ得た文学だとも思う。
ちなみにこの一説が塩屋の文化複合施設・海角で2023年より営業している舫書店の看板に使われていることをご存じだろうか?「本」という字の背面の文字列に注目してみてほしい。