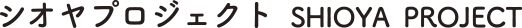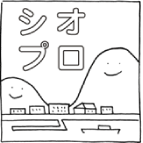『源氏物語』(紫式部・平安時代中期)
『源氏物語』(紫式部・平安時代中期)
「須磨」「明石」の巻が名高い『源氏物語』に果たして塩屋は出てくるのか。それを知りたくて、源氏物語の原文検索に「塩屋」の二文字を入れてみた。すると、ヒットしたのは須磨でも明石でもなく、「松風」の巻。とはいえ、やはり光源氏が明石に下った頃にまつわる文脈で、次のように出てくる。
乳母(めのと)の、下りしほどは衰へたりし容貌、ねびまさりて、月ごろの御物語など、馴れ聞こゆるを、あはれに、さる塩屋のかたはらに過ぐしつらむことを、思しのたまふ
これだけでは意味が取りづらいので、複数の現代語訳を以下に引用する。
まずは、与謝野晶子訳(1913)

「乳母も明石へ立って行ったころの衰えた顔はなくなって美しい女になっている。今日までのことをいろいろなつかしいふうに話すのを聞いていた源氏は、塩焼き小屋に近い田舎の生活をしいてさせられてきたのに同情するというようなことを言った。」
次に、谷崎潤一郎訳(1973)

「乳母も下って行った時は窶れた容貌をしていましたが、今は色香もととのって、このほどじゅうのお物語などを馴れ馴れしく申し上げますと、ああいう侘しい海人の塩屋の傍らで、よくまあ辛抱していてくれたと仰せになります。」
瀬戸内寂聴訳(2007)

「姫君の乳母も、明石へ下った頃はやつれていましたのに、今は大人びて器量も見違えるほど美しくなっていて、京に帰ってきて以来のお話などを、なつかしそうに申し上げますのを、源氏の君は、いじらしくお思いになって、あのような侘しい海人の塩屋しかない土地で、よくまあ辛抱してくれたとねぎらわれます。」
角田光代訳(2017)

「乳母の、明石に下った時にはやつれていた容姿が今は一段とうつくしくなり、ここ幾月かのできごとを親しげに話すのを感慨深く聞き、あの塩焼く小屋のそばで暮らしていた日々のことをねぎらうのだった。」
ご覧の通り、ここで出てくる「塩屋」は、塩焼き小屋・海人の塩屋であり、地名としての塩屋ではない。あくまで、海に近い侘しい田舎の象徴として使われる「塩屋」。つまり、厳密な意味で『源氏物語』は塩屋文学ではない。ただ、注意しておきたいのは、須磨・明石、とりわけ須磨と関連付けて、「須磨の塩屋」という形でこの「塩焼き小屋」としての「海人(海女)の塩屋」がほかの古典文学・絵画や衣装の意匠として度々見受けられること。『好色一代男』で世之介が塩屋で海女を抱くのも、これを踏まえてのことと考えられる。