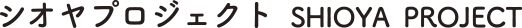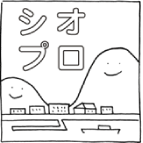高村薫『李歐』と重なる部分を多く感じる読後である。蛇頭とつながる中国人、舟でしか行けない無人島の射撃場のある豪邸と拳銃。ハードボイルド小説ではありがちな設定なのかも知れないが、あまり親しみがないと細部を混同してしまいそうだ。
第一章は、「平成七年(1995年) 九月十六日(土)」の出来事としてはじまる。
主人公の大学生、間嶋祐一は、「ガソリンの残量を思案しつつ、舞子駅から東にとぼとぼ歩いてきた。国道二号線は、JR神戸線、山陽電鉄と、かわるがわる浜側になり山側になりしつつ走っている。舞子駅から塩屋駅までの間は、国道二号線が一番海に近い。海岸沿いに建っている住宅やマンションがなければ、祐一の右側はすぐ海だった。ときどき更地があるのは、一月の震災で被害を受けた家だ。」
「どこまでも車の排煙でうんざりだった。思いついて、浜側にあるレストランとマンションにはさまれた細い路地を通り抜け、砂浜に向かってスクーターを押した。震災で倒壊した民家の再建限場を横目で見ながら、強くなる潮の香りを嗅いだ。」
塩屋の浜の辺りの描写である。
「テトラポットと花崗岩を敷き詰めた護岸の上を、スクーターを押して歩き続ける。少し気分がいい。(中略)砂浜に伏せたボートが並んでいる。シートでくるんでロープや鎖を巻き付けているところを見ると、しばらく使っていないのにちがいない。浜の東端には、波止を突き出した小さな漁港がある。漁船を係留してあるが、人の姿はない。」
と、ここまで読み進んで、やや首をひねってしまう。塩屋の海側の住宅街は狭く、集合住宅にしろ店舗にしろ、一軒入ればそれでおしまい、すぐに浜となる。だから、「レストランとマンションにはさまれた細い路地を」抜けたあとに「倒壊した民家の再建現場」が続く建物層の厚みは、垂水舞子にはあっても塩屋にはない。
また、「テトラポットと花崗岩を敷き詰めた護岸の上」は、かなり凹凸がはげしいため、「スクーターを押して歩き続ける」ことはそう容易ではないのである。しかも、まるで難なく漁港にたどり着いたようであるが、実際は護岸と漁港の間に小さいながら浜があり、砂地をスクーターを押して進むのは困難を極める。
とはいえ、易々と次の場面に繋がるのが小説の醍醐味である。野暮な詮索はやめて読み進めよう。
そこで祐一は、塩屋の港で古い舟の部品を磨いている男に出会い、その男にウィスキーを買ってくるように千円札を渡される。
「残り少ないガソリンを惜しみながら、塩屋の町に出て酒屋を探し回った。このあたりは昔からの別荘地だ。前は海、背後は鉢伏山やジェームス山。海と山にはさまれた景色の良い町だ。ジェームス山と呼ばれる山があるぐらい、外国人が多く住んでいたこともある。今でも洋風の古い建築物があちこちに残っている。コンビニを探すより、昔ながらの酒屋を探したほうが早いような町だった。」(→確かに!震災直後ならまだ酒屋があったが、今はコープに行って買うより他はない。駅の近くにはコンビニもない町なのだから。)祐一は酒屋で、千円で買える小瓶を一本買って、近くのガソリンスタンドでガソリンを補給して(→どこにあったの?!)海岸に戻り、男に渡してひとまずそのエピソードは閉じる。
この男は物語の後半で重要な役割を果たす人物ではあるが、明石の漁師が塩屋の漁港で船外機の錆を落とす作業をしているという設定自体が突飛な印象を受ける。この本の中でも触れられているが、漁師は縄張り意識が強く、所属する港によその舟が来ることには人一倍敏感なようだから、ショバ荒しとみられてもおかしくないような行為を当の漁師にさせてまで塩屋で二人を出会わさなければならなかった必然は何だろう。舞子から塩屋までの二号線沿いにガソリンスタンドはいくつかあったはずなのに、主人公にそれらを無視させ、スクーターを押して歩かせてまで!
この物語には、西宮のマリーナ、明石の林崎漁港、そこから行く孤島のプライベートな桟橋、下関港、そしてこの冒頭の塩屋の漁港の都合5ヶ所の港が出てくるが、他の港がいずれも船を発着させて前後の物語の進行と深く関わっているのに対し、塩屋のエピソードは、主人公と重要な脇役の一人を出会わせるためにだけ挿入されている。そのためか、場所の描写に若干の曖昧さが漂う。塩屋に住む者として、その不自然さは指摘しておきたい。
震災後30年近くが経とうとしている今の塩屋の町には、ガソリンスタンドも、コンビニも、使い走りがウイスキーを買いに行けるような酒屋もないが、配達専門の貴伝名酒店はある。